「VRで理解する発達障害」を実施しました

VR機器を活用して当事者の気持ちを体感
障害者週間に合わせて開催したイベント「パラスポーツと心のフェスティバル」(12月7日)内でVR機器(*)を活用し、発達障害の特性の一つ「聴覚過敏」を多くの方々に体験していただきました。
体験では、発達障害の特性を疑似的に体験することで、言葉だけでは伝わりにくい障害についての理解を深めるとともに、当事者が希望する配慮を具体的に考えていただきました。
*)「VR」とは…「Virtual Reality」の略で、「仮想現実」を意味します。専用のゴーグルで人間の視界を覆うように360°の映像を映すことで、実際にその空間にいるような感覚を得られる技術です
VR体験の流れ (1回15分程度)
1、事前に映像の内容を紹介(3分程度)
2、VR映像で疑似体験(3-5分程度)
3、映像の内容や障害特性の補足説明(3分程度)
4、当事者インタビューを視聴(3分程度)
5、アンケート
体験したかたの主な感想
息子の世界を知ることができて本当によかった

息子が聴覚過敏のためイヤーマフを使用しています。ドライヤーの音、バイクの音、シャッターを閉める音、お友達の泣き声などとっても辛そうな場面があるので、今回体験する機会があって、息子の世界が知ることができて本当によかったです。
この様な体験の場が増えて理解が深まればいいなと思います。
配慮の視点が欠けていたと気づかされました

発達障害の知識はあっても、想像でしかなかった。今回の体験で本人の心の状態を少しでも感じられ、理解が深まったと思った。
一見わからない生活のしづらさを、言いやすい工夫があると良いと思いました。自分の勤務先でも、そのような配慮の視点が欠けていたと気づかされました。
理解してもらうことがとても大切だと思っている

私の息子は自閉スペクトラム症で、感覚過敏がある。
幼い頃から感覚過敏があったと思うが、息子は自分の症状を他人と比べることができなかったので、親も、本人もそれに気づけなかった・
車のドアを閉める音、ボールをつく音、人の叫び声、花火や雷の音は飛び上がるぐらいびっくりすることがあると言う。一緒に出かけると、出先で私より多くの情報が視覚・聴覚から入っていって驚くことがある。外出が疲れることがよくわかる。音の問題は、時に周囲の人とのトラブルにつながることもある。まず理解してもらうことがとても大切だと思っている。このような機会を作って下さりとても感謝している。
対話を通して本人が希望する配慮を
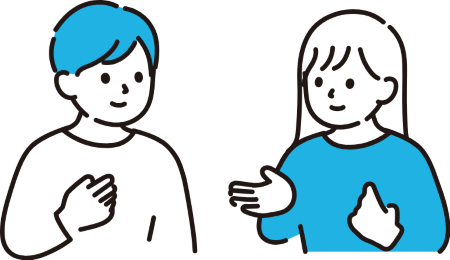
「心のバリアフリー」(*)を実践しましょう
発達障害のかたへの配慮を進める上で重要なことは、固定観念を抱かずに、その人の得意なことや苦手なことに目を向けること。そして、本人との対話を通して、希望する配慮を可能な範囲で実践してみましょう。
そのためには、発達障害に対して、私たち一人ひとりの理解を深めることが第一歩となります。発達障害の特性には、誰にでもあてはまるものも多くあります。明確に境界線をひくのではなく、多様な個性の一つであることを理解し、自分も「多様性」の中の一人だとイメージしてみてください。
(*)「心のバリアフリー」…さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え合うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部] 障害福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
- ご意見をお聞かせください
-




更新日:2025年01月24日